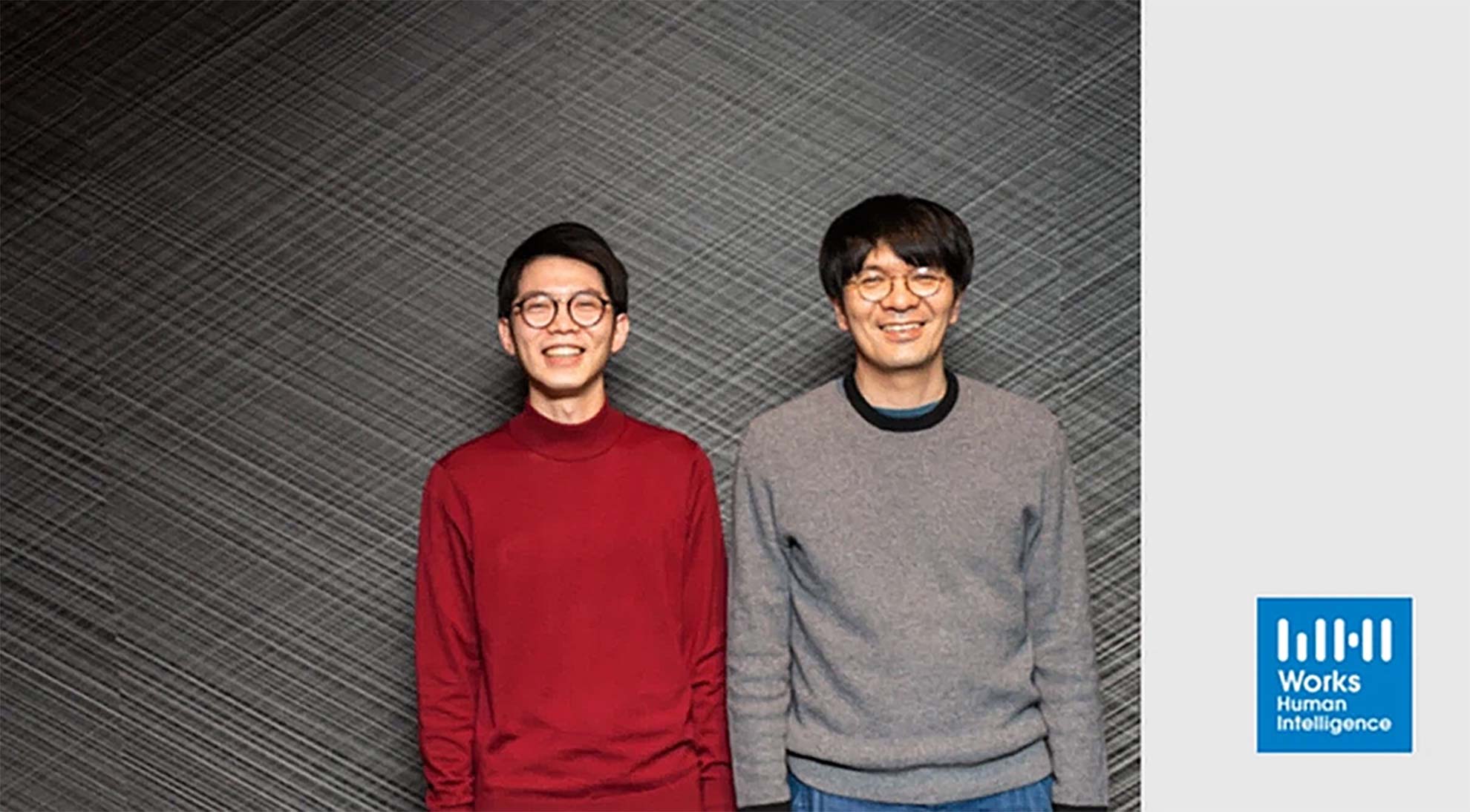
今注目のHRテック!大企業の複雑な問題解決に取り組むWorks Human Intelligenceの開発とは
2022.02.28こんにちは。採用担当の我如古です。
今回は、理系学生向け就活メディアLabBase( https://compass.labbase.jp/ )様に取材いただいた弊社開発職社員のインタビューをお届けします。管理職×若手という異なる視点から見たHRテックとWHIの、現在と未来の話です。
これを読んで「HRテックって面白そう」と思ってくださる方が増えたら嬉しいです!
※本記事は、LabBase「今注目のHRテック!大企業の複雑な問題解決に取り組むWorks Human Intelligenceの魅力」の内容を転載しています。
HRテック(HR
株式会社Works Human Intelligence
2019年に前身の会社からスピンアウトし、創業3年目という若さと20年以上売上を伸ばし続けてきた実績を持ち、大手法人を中心に約1,200法人グループに導入されているHRソフトウェアを展開する企業。
すべてのビジネスパーソンが「はたらく」を楽しめる社会を目指すため、システムとコンサルティングを用いてあらゆる業界の人事課題解決を行っている。
インタビューを受けた人

足達
Product Div. Attendance Management Dept.Dept Manager
2003年に入社以来、同社の勤怠管理製品の主力機能を開発。基盤技術開発やSREを経て、現在は勤怠管理製品部門を統括。日々日本企業の「はたらく」に向き合いHR製品の進化に取り組む。
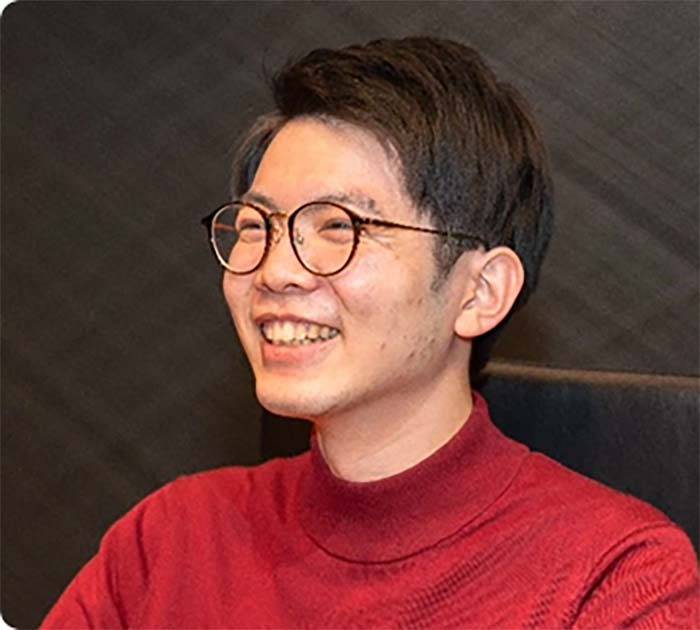
髙橋
Product Div. Payroll Dept.
理工学研究科卒。2019年に新卒入社。配属以来、年末調整など税に関連した従業員の申告・照会の機能開発に従事する。
あなたも使ったことがあるかも?450万人が使うWHIのHRテック

- 足達:
-
大手法人の人事・給与・労務管理といった企業運営に不可欠なバックオフィス製品から、従業員サービスやタレントマネジメントなどの人材活用まで幅広い領域をカバーする製品を提供しています。大手企業向け統合人事システム「COMPANY」は、最初のシリーズが出てからすでに20年以上。現在では日本の大手1,200法人グループに導入していただき、月間400万人以上の人事データ管理、給与計算をサポートしています。
学生の皆さんも、当社の製品を使ったことがあるかもしれません。アルバイトでは勤怠管理でタイムカードに打刻をしたり、シフトの調整をしたりしますよね。そういった記録や深夜帯で時給が変わる割増賃金の計算も、当社の製品で行うことができるんです。 - 髙橋:
-
私が担当しているのは、年末調整などの税金について従業員からの申告・照会を受け付ける機能の開発です。最新の機能「年末調整ナビゲーション」は、会社のPCやスマートフォンでの申請でペーパーレスを促進できるだけでなく、不慣れな人でもより簡単にミスなく申請できる最新機能で、従業員の負担軽減にも貢献しています。
実は、私も学生時代に当社製品を利用しており、「業務を楽にする技術があるのか」と興味を持ったことが入社の理由の一つです。

- 足達:
-
大前提として、ミッションには企業理念である「はたらくを楽しく」があります。私たちの製品やサービスによって、お客さまの「はたらくを楽しく」すること。そして、私たち社員一人ひとりが「はたらくを楽しむ」。それを実現するために大切にしているのが7つのValueです。
私たちの仕事は、単に製品を開発・提供するだけでなく、お客さまが抱える本質的な問題を解決すること。また、お客さまはもちろん社内で働く人たちに対しても、想いや大事にしていることを尊重しながら働くことを心がけています。 - 髙橋:
- 私が担当している年末調整の業務は、付加価値を追求するというより会社にとってやらなければいけない仕事です。ただし、それを「法律に沿ってできるようにしました」というだけでは本質的な問題解決にはなりません。そのため、もう一歩踏み込んで年末調整の仕事をもっと楽にするために必要な本質的なことを考えて、本当の意味での問題解決をしています。
HRテックの活用で「はたらくを楽しく」は加速する

- 足達:
- 戦略的な人材活用や組織に対するロイヤリティを上げることが喫緊の課題になっている今、会社経営においてHRテックはますます欠かせない分野だといえます。HRテックを活用することで「地に足のついた人材育成計画の計画ができる」とともに、より客観的なデータに基づいた人事が行えます。今後、HRテックを活用する企業はますます増え、市場としても成長していくでしょう。
- 足達:
-
今後は、テレワークの普及に伴って利用者が増えたTeamsやSlackなどのチャットツールと連携した勤怠管理ができるようにしていきたいですね。お客さまの利便性が上がれば、コアワークの業務に取り組むことができる時間が増えます。すなわち、お客さまの業務をより良いものにしていけるチャンスはまだまだある。そう考えています。
勤怠管理は毎日する必要がありますが、リアルタイムで入力してくれる人ばかりではありません。従業員が入力しやすいシステムを作ることで入力がスムーズになれば、人事は入力を促す必要もなくなります。昨今の働き方の変化により「出社しているのか在宅勤務なのかリアルタイムで知りたい」という新たなニーズも増えているので、そうした声にもキャッチアップしていきたいですね。 - 髙橋:
-
今、年末調整は電子化が進められています。国全体としてペーパーレス化していくことが求められているんです。しかし、今はまだ制度が始まったばかり。まだまだ過渡期で問題がたくさん残っています。
当社は、人事の方々が現場で困っていることなどを聞くことができる立場にあります。その困りごとを行政に届けることで、システムの面以外でもアプローチしていける経験や知識をもっと積み上げていきたいですね。
あえてのパッケージ製品が大手企業から選ばれる理由

- 足達:
-
大手企業を対象にした人事システムを提供しようとする場合、「制度が複雑であること」と「従業員の人数が多いこと」の二つが主に参入障壁となります。例えば、社内の人でもいろいろな働き方をしていて業態が違うため、それぞれに応じた勤務形態を管理する必要があるんです。また、イレギュラーなケースが起きたときでも従業員が少なければ手作業で修正ができますが、大手企業は従業員が数万人になることもあり、一つひとつ手作業で対応することはできません。
弊社の製品は、あえてお客さまごとにカスタマイズせず、基本的にパッケージ製品なのが大きな特徴です。単一の製品をお客さまに提供することで、他社が活用している機能を取り入れることを可能にしています。大手企業の場合、独自の制度を採用しているケースも多くありますが、そういった部分も尊重できるようになっているわけです。本来バックオフィス製品はコアコンピタンスではないので、差別化しなくても良いところですし、パッケージ製品として販売することで価格も抑えられます。
- 足達:
- 私たちはBtoBの企業。お客さまの業務をきちんと理解しながらアプリケーションを作るところがすごく面白いです。お客さまにメリットを提示するためには、HR領域や法律の知識、そしてお客さまの業務についても理解する必要があります。でも、難しいからこそのやりがいが魅力の一つ。管理職として、部下がモチベーション高く働くことができる環境を作れることにも楽しさを感じています。
- 髙橋:
-
年末調整は人事の一大イベントで、この時期には問い合わせ件数も増えるのですが、お客さまから「今年も年末調整が終わりました」と声が届いたときにやりがいを感じますね。
足達が言ったように、当社ではエンジニアの技術だけではなく、HR領域やお客さまの業務のことを理解する必要があります。入社後も日々勉強なのですが、仕事をする中でエンジニアとしての技術や業務知識を増やしていく過程も楽しんでいます。
チャレンジを推奨する文化の中で若手が活躍
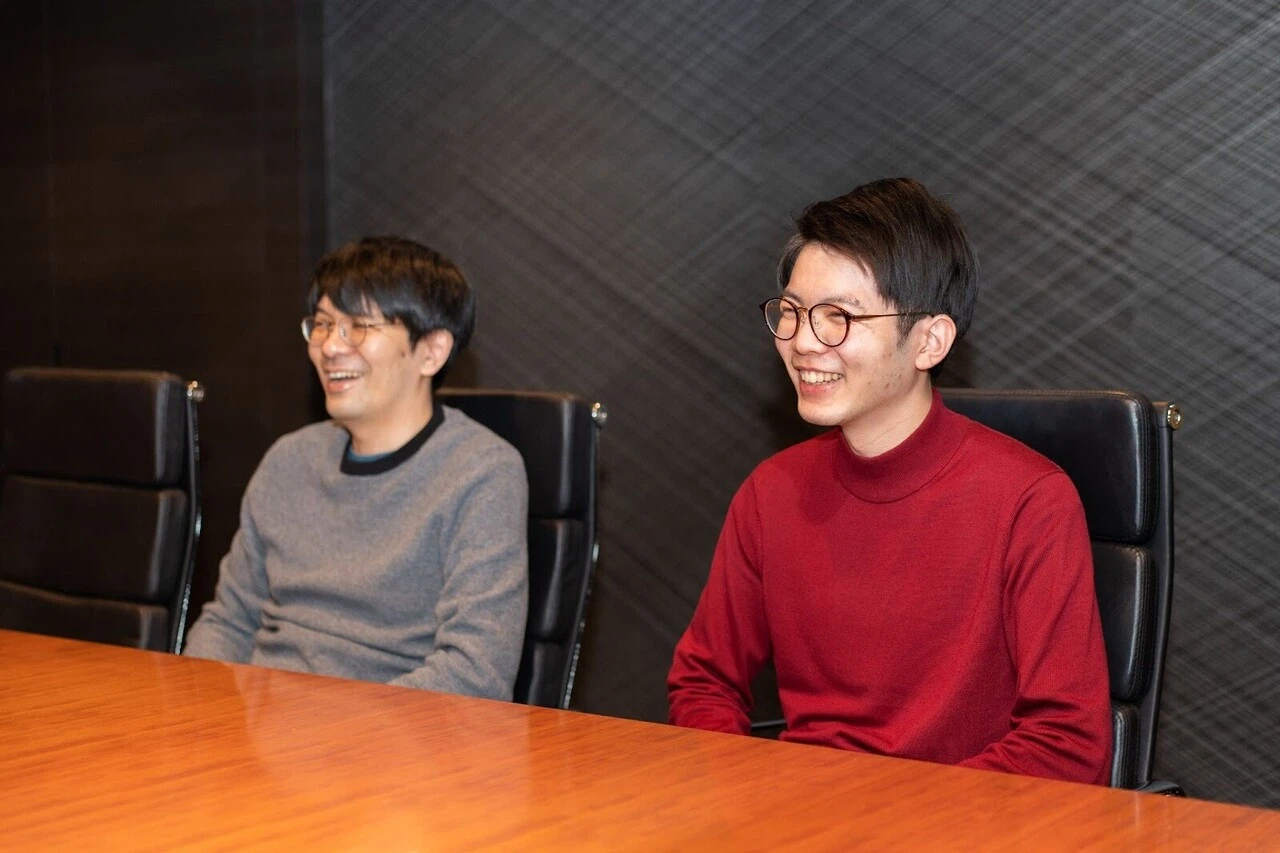
- 足達:
-
当社には失敗も許容した上で、チャレンジを奨励する文化があるんです。「若手だから」とやることを強制したり、「やりたい」と言っていることに対して「入社◯年以上じゃないと携われない」ということはありません。若手のうちから責任感のある仕事にアサインしてもらえる環境があるので、スピーディーな成長を求めている人には魅力的だと感じています。
もちろん、明らかに力不足だと感じるときはチャレンジするまでのステップを提案することもあります。ただ社内で求められているのは、技術や知識をどんどん身につけて担当開発者になってもらうこと。入社時点で完璧である必要はまったくなく、成長したい気持ちがあれば積極的に挑戦していけるフィールドが用意されています。 - 髙橋:
-
私は2019年入社の3年目。若手ながらも大きな法改正に対応するための機能の設計からリリースまで担当できました。先輩から引き継いだ業務でしたが、そのまま引き継ぐのではなく、「お客さまが使いやすくなるためにはどうしたら良いのか」をゼロベースで考え直しながら進めました。
主担当となると今までの業務とは重みが違い、法改正の内容もより深く知っておく必要があるため、省庁のウェブサイトなど、さまざまな情報を見ながら制度の理解を深めました。法律の解釈や業務想定にはまだ甘いものがあることを実感しましたね。社内発表の前に上司や社内の法律の有識者に相談させてもらいながら、ブラッシュアップを重ねてリリースすることができたときはうれしかったです。
- 足達:
-
われわれの仕事は、技術を追求するだけの仕事ではありません。技術を生かしていかにお客さまにメリットを提供できるかが大切。だから「お客さまの問題解決をいかにできるか」を考えることに面白さを感じる人に魅力的な仕事だと思っています。
問題解決への意識は、開発を行う技術者にとても大事なことです。そこに自分の技術を生かしていきたいと思う人には当社がマッチすると思います。 - 髙橋:
-
ソフトウェアの技術だけではなく、HR領域やお客さまの業務について幅広く学んでいく必要があります。そのため、何でも貪欲に知識を吸収していく姿勢がある人に向いていると思います。
問題解決と研究のプロセスは、非常に似ているんです。研究するときも、データから仮説を立ててそれを検証していきますよね。その経験はお客さまの問題解決にも役立てることができます。研究が好きな人には合うはずですよ。
編集後記
HRテックを活用して、「はたらくを楽しく」を実現するWorks Human Intelligenceには若手のうちから責任感のある仕事に携われる環境がある。今後伸びていくことが期待されるHRテックの分野で若手のうちから活躍したい人にぜひ挑戦してもらいたい企業だ。研究で学んだプロセスを、今後はお客さまの問題解決に生かしてみるのもいいかもしれない。