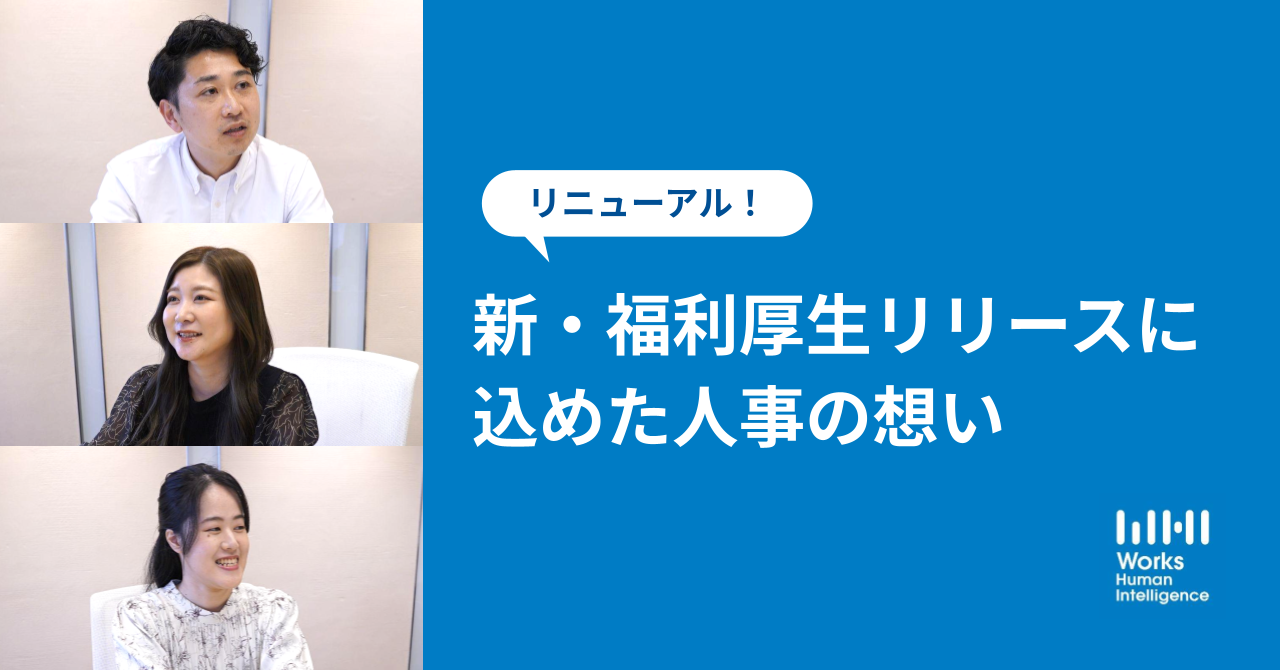
新・福利厚生リリースに込めた人事の想い
2025.04.14こんにちは😊 株式会社Works Human Intelligence(WHI)、採用広報担当です。
今回の記事では、「新福利厚生プロジェクトの裏側」をご紹介したいと思います。
当社のVisionの1つに「社員が成長する環境を作り、その成長にコミットし、我々が最も『はたらく』を楽しんでいる」があります。
これを実現するための要素の1つが、社員のはたらく環境を整える「福利厚生」です。
当社では、社会の変化を受けて福利厚生をアップデートするプロジェクトが発足し、2025年2月に新たな福利厚生がリリースされました。
今回、プロジェクトの裏にどんな想いがあったのか、担当者に聞いてきました!
1.働き方と福利厚生の変化は連動する
- 山岸:
-
最も大きな背景は、「社会がどんどん変化していっている」ということです。私がWHIに転職してきた当時、当社の福利厚生は充実していると感じたので大きな課題があるとは捉えていませんでした。
しかし、社会の動きに応じてキャリア観やワークスタイルはどんどん変化し、社員のニーズも変化していきます。だからこそ、その変化に合わせて福利厚生もアップデートしていかなければならないと考えて本プロジェクトが始まりました。
- 山岸:
-
そうなんです。だからといってがむしゃらになんでも対応すればいいというわけではありません。
そこで、社内で初の福利厚生に関するアンケートも実施し、制度設計では以下の点を重視しました。
1. WHIの福利厚生としてあるべき姿を改めて定義すること
2. 社員の声である福利厚生アンケートの結果を丁寧に分析すること
WHIの福利厚生としてあるべき姿をベースにしながら、社員のニーズにマッチする施策は何か、経営陣と何度もディスカッションを重ねました。
社員の要望を単に反映するだけだと会社としてあるべき姿と合わなくなるし、会社の考えだけで策定しては社員のニーズとは逸れる部分も出てきます。
このバランスが取れていないと、会社が制度を導入しても活用してもらえないという事態が想定されます。それはもったいないですよね。
2.「WHIらしさ」にこだわった福利厚生コンセプト
- 山岸:
-
そこが難しいポイントでした。他社をベンチマークし、施策を検討したのですが、WHIの福利厚生は他社の福利厚生と比べても遜色ない状態でした。
そのため、より「WHIらしさ」が確立されるような福利厚生にするべきなのではないかと考えたんです。
- 山岸:
-
やはり「社員の成長にコミット」するという点が「らしさ」だと思います。
この「WHIらしさ」を体現するために、新福利厚生では「自律的な成長の支援」「心身の健康の支援」「多様なライフプランの支援」という3つの軸をベースに施策内容を検討しました。
ただ、ここに行きつくまでに何度も議論を重ねていて、議論は何周もしていました 笑
あるべき姿を定義していくってとても難しいなと痛感しました。
- 山岸:
-
当社が会社として「どうあるべきか」という原点から考えるようにしました。
WHIでは「お客様」「社員」「会社」の3つの成長を目指すという会社の大方針があり、この3つに貢献するために、「Fair Treatment & Equal Opportunity」という考え方を軸に評価制度や勤怠制度などの人事制度を設計しています。
そして、人事制度や福利厚生、採用、育成などのさまざまな人事施策を通してMission・Visionの実現を目指していくという流れです。
ではその中で、福利厚生はMission・Visionを達成するためにどうあるべきかと考え、「自律的な成長」「心身の健康」「多様なライフプラン」という3つの軸に行きつきました。
- 山岸:
- ここは、当社の福利厚生に対する考え方の基礎になる部分なのでとても慎重に検討しました。私たちだけでも何度も議論しましたし、経営陣とも何度も議論しました。時には一周回って元の案がいいのでは?いや、この要素もあった方がいいのでは?となることもありました 笑
- 櫻井:
- ありがとうございます。社員には3つの重点領域をしっかりと伝えたいと思い、そのための表現も話し合いを重ねたので、伝わっていて嬉しいです。
- 石原:
- 運用面の検討は2024年の12月から本格的に動き出したのですが、新しい福利厚生を社員に早く伝えたくて、かなりタイトなスケジュールで検討を進めたことが記憶に残っています。無事に2月にリリ―スできて良かったです。
3. 社員の「成長」にコミットする福利厚生
- 山岸:
-
そうですね。「自律的な成長」という観点では、書籍購入補助制度や研修の費用補助、資格取得支援制度などがこだわりポイントでしょうか。
社員が自身で成長したい方向性を考えたときに、それを支える基盤を提供していきたいと考えています。
社員が自律的にキャリアを考えることが根付いている「WHIらしさ」のあふれた制度だと思います。
ほかにも、当社の社員が利用できるカフェテリアプランのポイントの増加もあります。
このカフェテリアプランでは旅行や健康支援、カフェテリアプランでサポートされているものがポイントで購入できます。
社員のアンケートでさまざまなニーズがあることがわかったので、それに応えた施策の1つです。個人の状況に応じて幅広く活用できる施策として強化しました。
- 山岸:
- ありがとうございます。ポイントは毎年付与されるので上限いっぱい使ってくださいね!
- 石原:
- ベビーシッター補助制度があります。年間の上限金額が上がったり、まとめての利用ができるようになりました。キャリアと育児のどちらかではなく、両立していきたいというニーズからできた制度ですが、今回の変更によりこれまで以上に使いやすくなるのでもっと社員に利用してもらいたいですね。
そのほかの福利厚生制度はこちら▼
https://www.career.works-hi.co.jp/corporate/system/
4. 社員の「使いやすさ」にこだわった制度運用
- 櫻井:
-
私は設定や運用面での検討が思い出深いです。
これだけこだわって作った福利厚生だからこそ、多くの社員に使ってもらいたいと思っています。しかし、申請方法がわかりづらかったり、面倒くさかったりすると使ってもらえませんよね?従業員体験の良い福利厚生運用を行うために試行錯誤しました。
制度の中身だけではなく、社員が実際に使うことを想定して提供することが重要だと考えています。
- 山岸:
-
そうです。福利厚生の数が多いからこそ、社員としては全てを把握することが難しいです。
そこで、「こんな時は何が使えるか?」という切り口で福利厚生ガイドブックを作って社員に提供しました。
- 櫻井:
-
そうなんです。例えば私が対応したものだと「ファミリーサポート休暇(※)」のアップデートです。
従来は子どものための休暇を想定していましたが、今回のアップデートで配偶者の看病や家族の介護も対象になりました。この変更によって利用できる社員も増えて非常に良かったなと思います。
(※)ファミリーサポート休暇…家族の看護、介護、予防接種や健診などに利用できる休暇を付与します。(年間最大10日)
一方で、よく利用する通常の有給休暇とは別の休暇になるので少しオペレーションが異なります。
通常の有給休暇はいつ取得するのかという情報だけあればいいというシンプルな申請方法です。しかし、ファミリーサポート休暇は人事側の管理のために「取得理由」を「看護、予防接種や健康診断、学級閉鎖、入園(入学)式・卒園(卒業)式、介護関連」から選択してもらう必要があったり、対象家族を「配偶者、子、父母・義父母、祖父母・義祖父母、兄弟姉妹・義兄弟姉妹、孫」から選択してもらう必要があったり、普段の有給申請とは異なる項目が必要です。
そこで、社員が間違えることなく申請が行えるように申請画面に注意書きを入れて、複数の資料を参照しなくてもいいように工夫しました。 - 山岸:
-
そうですね。社員が使いやすいように運用設計していくことも非常に重要であり、難しくもありました。福利厚生は中身を決めて終わりではなく、実際に社員が使いやすいか、使ってもらうためにはどうしたらいいかまで考えていくということが大事で、私たちもそこにこだわりを持ちました。
例えば…
「専門知識を取得したい」
→書籍購入補助制度・オンライン学習(GLOBIS・Udemy)・スクールやセミナー(福利厚生クラブ) …etc
「出産・育児に関するサポートを受けたい」
→出産手当金・配偶者出産休暇・ファミリーサポート休暇・ベビーシッター補助 …etc
その時の社員のニーズに合わせて使える制度をわかりやすくまとめています。 - 石原:
-
あとは少し細かいですが、リリースする福利厚生が法的に問題ないかという点もしっかり確認しました。社員にとって良いからという理由でなんでもできるわけではないんです。
法的な観点も含めてチェックしたり、グループ会社との調整も行っていました。
――会社として制度をリリースするということは中身を考えるだけではなく、法的観点はもちろん社員の使いやすさなど考慮すべき点が非常に多いんですね。
5.リリースがゴールじゃない、変化を続けることが重要
- 山岸:
- 今回のアップデートで終わるのではなく、定期的に社員のニーズや利用状況を把握してどんどんブラッシュアップを続けていきたいと考えています。冒頭でもお話しした通り、ニーズはどんどん変わっていくため、その変化をキャッチしていくことが大切だと思っています。
- 石原:
- 福利厚生ガイドブックについても、社員のフィードバックを反映しながら改善していきたいと思っています。社員の皆さんの率直な意見が今後の改善にもつながると考えています。
- 櫻井:
- そうですね。福利厚生に関するアンケートの中でもすでに利用できる制度があるのに知られていないという意見もありました。今回リリースした福利厚生ガイドブックを通じて、より多くの社員に制度を知ってもらいたいと考えています。
- 山岸:
- 個人的な想いとしては、将来的にトータルリワードで業界のリーディングカンパニーを目指していきたいと考えています。福利厚生面からも高く評価される会社になりたいですね。
――これからもどんどんブラッシュアップしていくと思うと期待も高まり、未来が明るくワクワクしますね。
本日はありがとうございました。私も一従業員として今回作っていただいた制度をたくさん利用したいと思います!
今回は当社の新福利厚生プロジェクトの裏側をご紹介しました!
「社員の成長にコミットしていくこと」は当社が大事にしている考え方の1つです。
これを支えるのは仕事内容や若手の裁量だけではありません。人事制度や福利厚生も含め、会社全体で社員のはたらく環境を作っていることが少しでも伝われば幸いです。